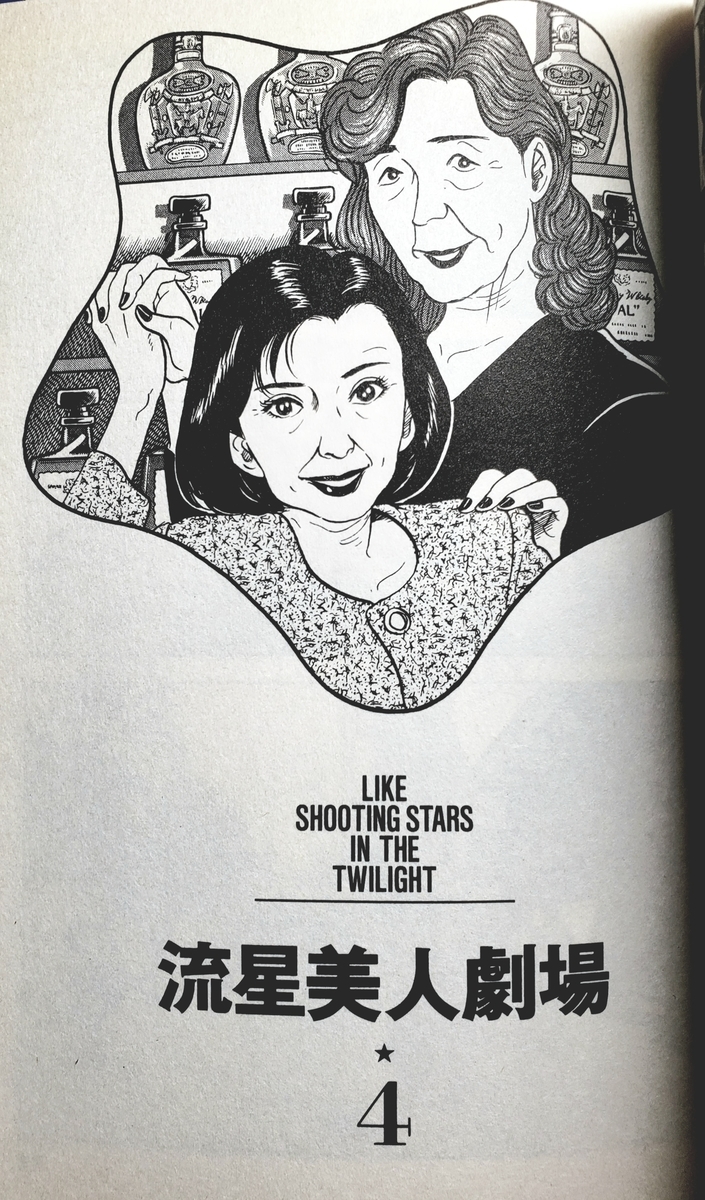1994年10月に発売された雑誌『STUDIO VOICE』の特集は「パリのジャズ物語り」。
フランスのジャズの歴史について、多数の執筆者が寄稿している。シャンソンとジャズの関わりについても触れられていて、興味深く読んだ。
まず触れておきたいのは、ジャズの発祥地であるニューオリンズは、かつてフランスの植民地だったことだ。白人男性と黒人女性(いわゆる愛人である)の間に生まれた子供は「自由黒人」として、フランスに留学することなどが許されていた。しかし、アメリカが支配するようになると、黒人は一律に差別されてしまう。こうした人権抑圧のなかで生まれたジャズは、もとを辿ればフランスの音楽とは無縁ではないのだ。
フランスで黒人音楽であるジャズが流行したのは、第一次世界大戦だったという。フランスでは、自国の男性が戦死して減少するのを防ぐために、海外から「外人部隊」を募集した。そこに志願したアメリカの黒人たちがジャズをもたらしたのである。アメリカでは、白人と黒人が一緒に戦うことはできなかったが、フランスでは対等に扱われたのであった。
第一次世界大戦後は、ロシアのバレエ「バレエ・リュス」がフランスに進出するなど、非西洋文化が席巻していく。そのようななかで、黒人ダンサーのジョセフィン・ベイカーが活躍するなど、黒人の文化がフランスで認められていき、ジャズもブームになってゆく。
しかし、フランス人が求めたのは黒人文化の「野蛮さ」であり、人種差別には何ら変わらないものであり、やがてブームは去り、同時に反発を招いたことは、本書でも触れられている。
ジャズギターの大家、ジャンゴ・ラインハルトがフランスで活躍したのは、この時期である。彼はジプシーの遊牧民で、幼少から楽器の才能に溢れていた。パリで活躍するも、火事で左手の指2本が動かなくなってしまう。しかし、彼は残りの3本指でギターを弾くテクニックを編み出して独自のスタイルを確立し、白人がジャズを演奏できることを証明した。
彼は、歌手のジャン・サブロンと組んで楽曲を発表するなど、シャンソンとも縁が深い。
シャンソンとジャズを融合させたのは、歌手のシャルル・トレネである。彼は、ジャズに影響を受けた楽曲を数多く作曲し、ワルツの三拍子が基本だった従来のシャンソンのスタイルに、新たなメロディラインをもたらした。
1937年、リス・ゴーティの前座で劇場に出演したトレネはこれらの楽曲を披露し、観客からの熱狂を受けてワンマンショー状態となった。ゴーティはぶちギレて帰宅してしまい、警官隊が劇場に出動した。そのとき、彼が歌った楽曲のなかの掛け声から、ジャズ狂いの若者のことを「ザズー(zazous)」と呼ぶようになったという。
このザズーが躍動するのは、第二次世界大戦下であった。フランスを占領したナチスドイツのヒトラーが、ジャズを下等な音楽として批判し禁じたのを受けて、反体制の若者たちを中心にジャズがひそかに流行した。また、ナチスが頭髪管理令や質素な国民服を強制したことに反発し、前髪を大袈裟にカールさせた長髪に、耳元まで立てた襟、長い上着、短いズボンやスカート、腕にこうもり傘をひっかける「ザズースタイル」を編み出して、権力に抵抗した。
フランスの反権力、アナーキー精神は、シャンソンではなくジャズによって培われたのである。
戦前の若者文化としてのジャズ、そして戦時中の反権力としてのジャズの影響を受けたのが、ボリス・ヴィアンであった。
彼はジャズを聴くだけでなく、戦後に実存主義が起こったパリの文化の街サンジェルマン・デ・プレで自らトランペットを吹くことで、その精神を表現した(あくまでセミプロとしてである。トランペッターとしての彼の評価は高くない)。しかし、彼は持病の心臓病が悪化し、トランペットが禁じられた。そして彼は、ジャズの評論を書くようになり、アメリカから来たジャズプレイヤーを紹介する役割を担うようになった。
また彼の反権力の精神は、自作のシャンソン「脱走兵」などにも表れているといえよう。
そして、ジャズとシャンソンの関係といえば、ジュリエット・グレコと、アメリカのトランペッターのマイルス・デイヴィスとの蜜月である。
1949年、パリで開かれた第1回国際ジャズ祭のゲストに呼ばれたデイヴィスは、その合間にグレコのコンサートを観に行った。そこで二人は出逢い、恋に落ちた。デイヴィスは2週間フランスに滞在したが、その間ふたりは愛し合った。そして、人種差別が待ち受けるアメリカに帰ることを嫌悪し、麻薬に溺れた。
それほどまでに、アメリカの黒人差別は酷く、差別を受けないフランスに憧れるジャズマンは当時沢山いたという。
1957年、デイヴィスは再びフランスを訪れ、ルイ・マル監督のヌーベル・ヴァーグの代表作「死刑台のエレベーター」の音楽を担当する。それは、映画を見ながら指定されたシーンでトランペットを即興で吹くというものだった。
これこそ、ジャズの即興性というものだろう。
以来、映画の音楽でジャズが使われることが増えたという。
そして、おそらくこのあたりからフランスでジャズのブームが低迷していったと思われる。この時期、シャンソンはジルベール・ベコーが頭角を表していたが、彼はジャズ調よりロック調の人だ。
現に、本書でもこの時期以降のことになると、執筆陣の筆が失速している。ジャズブームの衰退は、本書の「パリのジャズ物語り」というテーマにそぐわなくなっていったのだろう。
本書の最後のページには、現在のフランスのジャズの担い手として、クレモンティーヌやアルチュール・アッシュなどが紹介されているが、さすがにこれには疑問符がつく。
フランスとジャズの関わりを見ると、人権問題と反権力がテーマとして浮かび上がるのが分かる。生きにくい世の中を歩んでいくために、文化が武器になることを改めて感じた次第である。